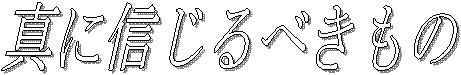
1
観察報告その1
名前:キリィ・マクラーレン
職業:警視庁警備部特殊捜査班所属。
階級:警視
観察日誌:今現在、彼は平凡ながら警視庁の仕事をこなしている。現在は恋人、“イヴ”がいる。
人類は高度に成長を遂げた。科学分野においてそれは顕著であり、特にロボット工学においてその真価を見せる。毎秒1万キロバイトの高速通信を備えた人間に酷似した存在。アンドロイド。
元々真空管から発展したその無機質な物体は、徐々に生気を帯び、四肢を持ち、思考を持った。そして、その目に入るものを学習し、習得し、人間社会に溶け込んでいくのは容易であった。
持てはやされるその実験はメディアに大きく取り上げられた。
製作者は語る。
「ここにあるアンドロイドはまだ機械の域を出ない。もし機械として真に進化を果たしたとき、それは人間と同じものとなるだろう」
人間の愚考が為せる物である。
人間を作るクローン技術は数年前に完全に放棄された。しかし、パーツとしての製造管理はなされ、それはアンドロイド、バイオロイドと呼ばれる物達に流れていく。しだいにそれらは人間との区別がつかないほどに精巧なものとなった。しかし、唯一違うもの。それは主への絶対的な服従と共に、その腕に刻まれたバーコード、“シリアルナンバー”であった。
そんなアンドロイド達は「第二世代」と呼称された。「第一世代」と違うのは、学んだ事を応用することにより、精密な仕事をこなせると言うことにある。
“彼ら”、“彼女ら”は一般社会へと浸透していくのは早かった。あるものは人足として、あるものは仕事の手伝いとして、またあるものはスラムへと流れ、軍事施設にも買われていった。
数年が過ぎた。
用のないものは捨て去られ、また廃棄される。意思を持たず命令のままに動く“彼ら”、“彼女ら”にとってそれもまた主の下した命令である。反抗はできない。そんな中、社会の中に様々な動きが起きた。アンドロイド達の保護を訴える声が起きたのだ。
むろん“彼ら”、“彼女ら”にとっては関係のないことであった。
それも逆に利用された。鎮圧の為に戦闘調整のされた“彼ら”が投入され、完膚なきまでに叩きのめしてしまったのだ。
メディアがこれを逃すはずもなく、第一面で叩いた。軍事に利用される者たちが可哀想だ、軍事に投入されるくらいなら作らないほうが良かった。しかし、すべては後の祭りである。
そんな腐敗した社会に生まれた団体、“マリオネット排斥団体”、“アンドロイド擁護団体”。
この2団体の抗争は長く続いた。街中でこれ見よがしにアンドロイド達を集め、火を放つ排斥団体。非合法商売に買われていく“彼女達”を救助の名目で襲撃強奪する擁護団体。
世の中は、科学から作り上げた息子、娘達を巡って、終わることのない戦乱を起こしていた。
2
「おい、ユダ、ユダ!聞いてるか!?」
「ん……あ、あぁ、キリィか。なんだ?」
俺は同僚の声でパソコンから顔を上げた。
「なんだじゃねぇぞ!所長から通達があっただろ。」
目の前にいるのはキリィ・マクラーレン。まぁ俺の“同僚”ってやつだ。こいつと組んで数ヶ月経つが、まぁそこそこできるほうだろうという認識である。
「あぁ、排斥団体の連中がまたキャンプファイヤーやってるってやつか?」
キャンプファイヤー、俺達の間でそう呼ばれているのはアンドロイド達の望まれぬ火葬である。
「あぁ。しかも今回は場所が場所だ。あいつら、擁護の連中の前でバラバラにした挙句やりやがった。」
その表情は苦渋の色が浮かんでいる。アンドロイド達の痛みをその身に感じていると言うが、分かる気がする。俺自身、アンドロイド達と共存は出来ると思っているし、そうであって欲しい。
「行くぞ。一刻も早く!」
キリィに急かされて俺は警察署を飛び出した。パソコンに残っていた文書はきちんと送信してから。
そう言えば名乗ってなかったな。俺はユダ・ユリシィ。通り名は“ベトレイヤー”。裏切り者の意味だ。……心外だがな。
轟々と燃え盛る炎の中にはいくつもの人型が見て取れる。それら全てがアンドロイドのなれの果てなのである。むごい惨劇だ。しかもご丁寧に、
『この世にマリオネットは必要ない!』
などとスプレーらしきもので地面に殴り書きがされている。
「ひでぇことを」
燃え盛るアンドロイド達を前にキリィは二の句が繋げない。これまでに何度となくこういった現場には来ているが、その度に感傷に浸っている。彼自身科学が好きであり、アンドロイドに興味があった口なので当然と言えば当然だが。
「キリィ、見てないで消せ!」
「あ、あぁ」
俺に急かされて、彼は燃え盛る炎に手を向ける。
「召、水、流!」
人が聞いたら何を言っているんだという発言だが、これが彼の得た“力”だ。
俺達の前で、炎を包み込むように水の奔流が吹き上がったのだ。その水は炎を消し去る。
見ていたギャラリーが騒然となったが、それには取り合わない。
応援を呼んで到着する間、辺りを見回っていた彼だが、ふと、ある一点を見て目が留まった。
「イヴ!?」
いきなり恋人の名前を呼ぶと、走り出した。
彼女は燃えたアンドロイド達の目前に立ち尽くしていた。
「イヴ!」
キリィが呼ぶと、彼女はキリィを振り返った。
「……キリィ」
彼女の目には薄っすらと涙が浮かんでいる。
「何で来たんだ。お前」
彼女はそっと目を逸らすと、
「彼らの……悲鳴が聞こえた」
物言わぬ“彼ら”、“彼女ら”に対して彼女は人と同じ慈愛を見出している。幼稚園の保母をしている仕事のせいもあるだろうが、少し違うようだ。
「あぁ、酷い有様だ。」
「どうして……」
彼女はつぶやく、
「……人間とアンドロイド達は判り合えないのかしら、彼らが何かしたわけではないのに。」
「…………。人間てのは愚かな生き物なのさ。自分で作っておいて自分で破壊する。自分以外のものを否定する、まるでナチスのような連中みたいに。」
彼の思い入れ、と言ったら失礼だろうが、イヴに負けず劣らずアンドロイドに対する思いは強い。
しかし、数ヵ月後それは悲劇を持ってえぐり返されたのである。
3
観察報告その2:キリィを悲劇が襲った。恋人であるイヴが襲われたのだ。しかも、相手はアンドロイドである。とち狂ったマニアがアンドロイドの電子頭脳を改竄し、イヴの勤める幼稚園を襲わせたのだ。
多大な被害が出た。園児10人が惨殺され、30人以上が重傷を負った。そして、イヴも園児をかばおうとして標的となり、帰らぬ人となってしまったのである。
彼は失意のうちに行方を暗ました。俺は奴を観察しなければならいため、必死に探し回った。しかし、理由は他にもあった。
俺がキリィを見つけ出したとき、奴は完全に荒んでいた。そして、とんでもない事をやっていたのである。
『アンドロイド生産工場壊滅!謎の男の襲撃』
新聞にデカデカと載せられた文面に俺は驚かされた。紙面には生産工場で爆発があったが、その炎は工場を完全に灰にするまで燃やし尽くしたらしい。目撃者の話では、一人の男が燃え盛る工場を見つめていたという。そして、唐突に消えたと。
俺は衝撃を受けた。信じたくはないが、奴は“アンドロイドを消し去ろうとしている”。
まさか、失意のあまりアンドロイド達に恨みを持ったのか?人間の感情と言うのは解し難い物だが、こうも予想を超えてくれると困る所もある。そして、そんな連中に興味を引かれる俺もいるが。
とにかく、キリィはなんとしても探し出さなければならない。そうしなければ……。
俺がキリィを探し続けて一週間が過ぎようとしていた。すでに奴は他の都市にまで赴いて生産工場を破壊し続けている。しかも、邪魔するものは容赦なしらしい。そして、道行くアンドロイド達を捕まえては叩き壊すという最悪なところまで行ってしまっていた。
むろん、警察は彼を特Aクラスの指名手配にした。
そんなことをしても無駄なことは多分俺しか知らないだろう。奴は自由自在に逃げ回る“力”を持っている。となれば俺が見つけるしかない。
俺は今メインストリートに来ている。キリィの移動ルートを追えばよかろうと思っていたが、移動速度が異様に速いので後数分もせずにあいつはここを通るだろう。ここには芸を仕込まれた“彼ら”が、ストリートライブをよく行っている場所だからだ。
「ほんとに来るのか?」
同僚達に休日返上で集まってもらい、緊急に配備を敷いてもらった。
「確かにあいつは人間離れしている。けどよ、水芸が得意なだけじゃ、俺達が武装することはないんじゃないか?」
そう万が一の事を考えて彼らには武装してもらっている。が、
「あいつの“力”は水だけじゃない。全てを御する最悪の“力”だ」
口調も少し、緊張したものになる。
「はぁ?……なんじゃそりゃ。神でもあるまいし」
などと言い終わるか否かの時、近くで爆発音が聞こえた。
「何だ!?」
同僚の一人が上ずった声を上げた。それを最後まで聞かぬうちに俺は走り出している。
「……おい!どうする……」
その言葉が悲鳴にかき消され聞こえなくなる。その時、俺は彼の気配を明確に感じ取っていた。右往左往する市民の間をすり抜け、俺は遠巻きに何かを見ている人々の“頭上を飛び越えた”!
空中から見えたその光景、キリィがいたのである。
しかし、その手には鋭い切っ先を持つ剣を持ち、それに刺し貫かれているのはアンドロイドの一体。彼は剣を瞬間的に引き抜くと返す刀で胴をなぎ払った!その体はやすやすと剣を通し、次の瞬間2つに分かれたその体から炎が噴き出し灰となる。そう全ては一瞬。
「キリィィィーー!!」
着地した直後、あらん限りの声で俺は声をかけた。彼は俺の存在に気づいた。
「よう、久しぶりだな“ベトレイヤー”。元気してたか?」
「てめぇは……一体何をしているんだ!」
聞くまでもない事が俺の口をついて出た。しかし、言わずにはいられなかったのである。
「何を、か。……フッ、確かに何やってるんだろうな」
自嘲気味に彼はそう答えた。
「……ただやらずにはいられない、ってぐらいだな!」
いきなりベルトのナイフを抜き放つと、横手に向かって投擲する。そこにいたのは野次馬をしていたらしきアンドロイドを連れた人たちだった。しかし正確にその眉間を貫くはずだったそのナイフは甲高い音を立てて弾き飛ばされる。
一発の銃弾がナイフ等を撃ち落すには並みの集中力では足りない。むろん出来ない者がいない訳ではなかろうが、今の時点でそれが出来たのは一人。俺だ。
「……そうか。お前も邪魔するか」
静かに悲しい目で彼は言った。
「邪魔さえしなければ……」
全員の視界から彼が消える。そして、次の瞬間には俺は行動を起こしていた。人智を超えた加速をかけてアンドロイドを切り裂こうとするキリィの前に躍り出て、右回し蹴りで剣を弾き、さらに空中から放った左のかかとで一撃し、彼を吹っ飛ばしたのである。
「……な、なんで」
彼が身を起こした。その表情には驚愕の色がある。そして、その相手は俺だった。
「やめろ!お前がこんな事をしたって、何も変わらんぞ」
「くっ……!」
彼は理解より先に剣をとり、再び向かってきた。
「貴様に何が分かる!!」
向かってくるキリィに対し、俺は逆に向かって行った。彼の剣の射程に入り、彼が剣を振るう。しかし、動揺のせいか剣に冴えがなくなっている。しかし、普通の人を殺すには十分な速度でも、俺に対しては致命的だ。剣は空を切った。次の瞬間にはキリィの顔面に強烈なとび蹴りが入り、またもキリィは吹っ飛ぶ。
キィンと音を立てて俺の前に彼の剣が落ちた。
「……お前、やっぱり」
蹴られた場所をぬぐいつつ彼は身を起こす。そして、拾われた剣を見て動きが止まった。
「荒れてるな。この剣。血がこびり付いている上に刃が欠けている。
普通こんなになるもんじゃないんだが、相当くすんでるなお前。」
「返せよ……」
「これ以上無理な酷使を続ければ折れるぞ。そうなったら、どうなるか分かってるのか?」
「返せつってんのが、聞こえなかったのか!」
言い終わらないうちにキリィは突っ込んでくる。俺は、きびすを返すと人ごみを一気に飛び越える。そこにいた同僚に、
「後よろしく!」
そういい置いて、直に走り出した。その直後にキリィが着地し、目もくれずに俺を追いかけ始めた。
4
街中を疾風が駆け抜ける。縦横無尽に張り巡らされたキャットウォークのような街道。天を貫くような大型エレベーター。ビルの谷間、天空からの急速落下。
やがて、俺は足を止めた。
息一つ乱さぬまま、少し遅れてやってきたキリィを見やる。
「はぁ、はぁ、……くそ、どうなってんだ」
「いつもより力が出ない、か?自分で自分の能力を殺してるだけだろうが」
「ほざけぇぇぇ!」
一気に駆け込んでくるキリィだが、それはただ獣の突進のようだ。俺は身を少しずらし、足を引っ掛けて転ばしてやった。
「くそっ……、う」
身を起こそうとしたところに、俺は剣先を突きつけた。
「お前はイヴを弔うためにやっていると思っているようだが、……」
俺は静かに語りかける。
「……お前は思い違いをしている」
「……何を?」
剣を突きつけられたことにより、さっきよりは落ち着いた口調で聞いてくる。
「お前が殺すべきはアンドロイドを改造した張本人だろ。それをてめぇはアンドロイドが悪いように取りやがって、てめぇのアンドロイドに対する愛情ってのは結局それぽっちだったんだな」
「…………」
「確かに人間は愚かな生き物だ。だがな、愚かだと思っているうちは、自分のほうが愚か者だってことを忘れるんじゃねぇぞ。」
「……どういう意味だ!」
「信じていたものに裏ぎられたような顔してる奴が、血気に逸ってるってことだ」
「けっ、言うじゃねぇか。だがな、失われたものが戻らない以上、俺自身の気持ちってのはどうなる!」
今度はキリィが独白を始めた。
「そりゃ俺だってアンドロイドが好きでこの旅を志願したさ。けどよ、身をもってそれを裏切られたんだぞ。この責任てのはどこも取ってはくれねぇ……!」
「甘ったれてんじゃねぇ!!」
俺は怒鳴ると、剣を目の前に突きたてた。そして、キリィの眼前に顔を突き出した。
「責任だぁ?!ふざけるな!これはゲームじゃねぇんだ。何もかも思い通りになると思ったら大間違いだぞ!」
彼は呆気に取られて俺を見上げる。
「お前は何を考えてこの旅に参加した?何もかもが思い通りになるような事を望んだからか?否だ。
お前はこう言って参加志願したんだぞ。
――アンドロイドって物を一度でいいから見てみたい。ってな。」
「……な、なんでお前が知ってる!?」
その一言に今度は俺がハッとなった。年甲斐もなく熱くなったようである。
「ちょっと待て。お前、参加者の一人じゃないのか!?」
「ち……。しゃぁねぇな」
俺は立ち上がって、頭をかいた。
「答えろ!誰だ、お前は!」
突きたてられた剣を引き抜くと、俺の目の前に突き出す。
「同僚だよ、お前の。そして、あいつともな」
「…………。なるほどな」
俺の発言に納得し剣を引くキリィ。
「一つ教えてやろう。」
妙に沈んだ彼に俺は声をかけた。
「“第三世代”ってのを知ってるか?」
「あぁ、新しく出される新商品か。それが……?」
「発売目的は人間として生活の一部となること。そのために、心を持たせ、限界近くまで人間に近くするそうだ。」
「……心を持つ、だと?」
「メモリの処理にランダム性を持たせることで人と同じような思考をするそうだ。受動的な“第二世代”と違って能動性を持った“第三世代”は外見も中身も行動も人と見分けがつかない、ということらしい」
「それが、どうしたって言うんだ」
「プロトタイプが一体だけ製作され、実際に試験運用されていた。仕事を与えてデータを取っていたが、ある日を境に製作者も思いもつかなかったデータが取れたそうだ。“恋”ってやつさ。こればかりは設定でどうにかなるもんじゃないしな」
「…………」
彼は俺の言わんとすることが分かっただろうか。そうだといいのだが。
「この間壊れたが、メモリとCPUは無事だったそうだ。修理されて今待機状態にある」
「…………。まさか」
「……、バーコードは試験運用のために皮脂を被せる事で隠したが、番号はX−3E2V19E。呼称は『イヴ』。」
「どこだ!!」
キリィはほとんど半狂乱のように俺に掴みかかってきた。
「彼女はどこだ!」
俺はポケットからIDカードを出し、彼に見せていった。
「行ってやれ。このビルの20階だ」
扉の前に彼は到着した。額には汗を浮かべている。
そのビルは彼が破壊するはずだった、この町のアンドロイド研究所である。
震える手でIDをローダーに通す。認証がなされ、ドアが開く。
中には数人の研究者達がいた。そして、彼らが囲んでいるのは大きな円柱状のカプセルだ。機器に繋がれ、物々しい光景である。
科学者の一人がキリィに気づいた。すると、他の研究者達に声をかけて、さっさと別の出口から出て行ってしまったのである。
「……え、あ」
声をかけるまもなく一人にされたキリィは不安に駆られた。本当にここなのだろうか。
すると、目の前のカプセルから音が発せられた。蒸気を吐き、カプセルが起動したのである。
ゆっくりと扉が開いていく。じっとその光景を見るキリィ。そして、目を剥いた。
中に収められていたのは紛れもなくイヴであった。目を閉じて立っている。そして、その目がゆっくりと開いていく。
薄く開けられた白目に走査線が走り、黒目が現れる。瞬きをしてから両手を持ち上げた。まるで自分がここにいることが不思議でしょうがないといった顔である。
目の前の人物に焦点があった。その人物の検索がされる。一件だけ該当があった。膨大な量の情報が解凍され、メモリの中を駆け巡る。
ゆっくりとカプセルから進み出る彼女。その目はキリィを見つめたままである。そして、一糸纏わぬ姿の彼女はキリィの前に立った。
「イヴ……。なのか?」
名前が呼ばれた。ただそれだけの処理にCPUは熱を持ち、熱循環のため潤滑剤のめぐりを早めた。メモリから送られてくる挨拶行動の項目から最適な選択がされる。しかしここでランダム性が発生し、命令は取り下げられ、一般行動の項目から命令が選択された。
挨拶発言の項目から最適な挨拶が選択されたが、ランダム性が発生し、友人発言の項目に変更される。感情制御のアクセスがランダム性によって混乱し、悲しみと嬉しさが二重選択される。
一瞬の処理の後、それを実行に移す。
彼女はゆっくりと両手を持ち上げると、キリィの首に手を回し、抱きついた。
「……イヴ」
彼も彼女を優しく抱く。その体に流れるのは潤滑剤だが、熱処理のせいで今は上気している。
そして、最終的な実行命令が下された。
「……キリィ」
それは、彼の名を呼ぶこと。
最終観察報告:キリィ・マクラーレンの今回の行動についてはコメントを差し控える。強いて言えば、結局のところ愛に境界無しと言うしかないのだが。まぁ、経験できる事象の中では特異な方であろう。今後の観察は必要なしと判断し、これよりそちらに戻る。事後処理のほうよろしく頼む。
ところで、そっちのほうだが、あの6人組。お前、世話焼きすぎじゃないのか?他の連中から睨まれてるの気づいてるか?
ま、俺の知ったことじゃないけどな。以上だ。
監視官:ユダ・ユリシィ
――End――
*******************************
あとがきな事ですが
るすたあ様リクエスト、「天使の敵・同業者」がテーマと言うことでこんなものを書いてみました。
いやぁ、おくれてすみませんでした。(ペコリ)
今回の作品でこだわったこと、機械は人を愛せるか、人は機械を愛せるか、ということ。表現できたとは思ってません。未熟ですから。(死)
これを書く上で私は「アミテージtheサード」を参考にしました。先日見たばかりで印象強く残っていたので、これだ!ってことで。
まぁ、戦闘書くのが好きの自分が恋愛を書くと、ベタベタになってしまうという典型的な例?
ワールドカップが迫ってきましたが、はっきり言って自分は興味なかったりします。どうしてか。小説が溜まっているからです。
あぁ!石投げないでぇ!!
まぁ、なんにしても、書かないと読んでくれる方に失礼ですからなんとか書いてます。
てなわけで、今回はこれにて失礼。
2002/05/14