
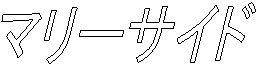
3・女王フレイア
懺悔室から出てきたマリーの前に現れたのは白を基調とした服を来た壮年の騎士だった。先ほどの人とは違う。
「あの、何か」
「さきほど酒場であなたを見かけました。あまり歓迎できない騒ぎでしたが」
「あぁ、すみませんでした。ご迷惑をおかけして」
言って深々と腰を折るマリー。
「いえいえ、そんなに恐縮されても困ります。
あんなことは日常茶飯事なので、特に気にはしていません」
「はぁ・・・」
「あなたは見たところ外からおいでになったんですね」
「はい。少し遠いところから」
ほんとはかなり遠いのだが・・・、
「それなら、ヴァンパイアバーには注意してくださいね」
「ヴァンパイアバー・・・・、ですか?」
ヴァンパイアと聞いてマリーの表情が緊張した。
「ええ、両国で頭を悩ませているのですが、昼間ヴァンパイアたちが姿を隠すのに使っているのです。
特徴としては、昼間なのに暗くて、客が不自然に多いということぐらいです。
素人目には分かりにくいですが」
「そうですか」
「とまぁ、私の話はこんなところです。とにかく今後注意してくださいね。」
と、騎士は背を向け去っていく。
「あぁ、忘れてました。・・・・・・」
男は振り返り、
「私はクルドウェストで騎士をしてます、ライアーと申します。ご縁があればいずれ」
今度こそ、彼は教会の扉から消えていった。
「ちょっと待て!お前!」
乱暴な声で男が声をかけてきた。マリーは教会を出て、いざ次の町へでもと思っていたところだ。
男のほうを向くと、これまた白基調の騎士服だ。
「お前。さっき、酒場で騒ぎを起こしていたな。」
「はい。そうです」
きっぱりと事実を認めるマリー。その物言いに男は一瞬口篭もった。「嘘を言うな!」とでも言いたかったんだろう。
「お前、ちょっと来てもらうぞ。取り調べる」
「はぁ、分かりました」
そういってその騎士について行ったところ、小さな詰め所だった。
「入れ」
ぶっきらぼうな態度は変わらず男はマリーを中へと入れる。
と、中には先客がいた。これも女性で、質素な服を着ている。紙は栗色で腰まである長い髪だ。
「ん?お前、そんなところで何を突っ立ってる」
そう発言したとたん、あたりにいた騎士が、いっせいにこの男を見た。
そして、その女性は振り返り、微笑を浮かべながら、
「あら、すいません。邪魔でしたか?」
鈴を鳴らすような声で彼女は言った。抜けるような美人だ。マリーの髪を栗色にしたら似ているんではなかろうか。
そして、彼女を見たとたん男の態度が豹変した。
「こ、こここ、・・・これは女王陛下!!?」
「さ、通ってくださいな」
と、脇へとよける彼女。しかし男は彼女の前に平伏し、
「し、失礼いたしました!!知らぬことはいいながら…!」
「・・・・あらあら。いいんですよそんなに誤らなくて」
常に微笑を絶やさない彼女。相当心の広い女王だ。
「フレイヤ陛下もこう仰っておられる。いいかげんに頭を上げよ」
後ろから現れた壮年の騎士。っと・・・、
「あ、先ほどの・・・ライアーさんでしたっけ?」
「ん、おお。これはお嬢さんですか。こんなところにどうしました?
まさか、こいつに連行されたのですか?」
「はぁ、・・・・そうです」
「まあまあまあ・・・」
陛下と呼ばれた女性が声をあげた。
「いい方じゃありませんか。あたしと似てますねぇ」
「あ、いえ・・・・」
性格はどっこいどっこいのようだ。
結局、あの騎士はまた見回りに戻され、マリー達は近くの喫茶店で話をすることとなった。
「まあまあ、お一人で旅をされてるんですか?」
「はい。御主人達もどこかにいると思うのですけど」
「ご主人・・・ですか?」
マリーは、ハッとなった。
「いえ、友人です。たまに癖で・・・」
「そうですか」
あっさり納得する陛下。マリーは胸を撫で下ろす。
「それで・・・お聞きしたいことがあるのですが」
「はい、なんでしょう」
「先ほど、そちらの騎士さんから聞いたのですが、ヴァンパイアバーってなんですか?」
「ヴァンパイアバーをご存じないんですか?」
「はい、実はそうなんです」
彼女はライアーと顔を見合わせた。どうやら知らないほうがおかしいらしい。
「まぁ、ご説明と言うほどのものでもないんですが・・・・、
街中で昼間なのに異様に暗く、やけに人の多いところは避けたほうが良いとしか、私は・・・・」
「日の光がヴァンパイアの弱点になっていると言うのはご存知でしょう。日の光を避ける巣窟みたいなものです。
やつらは人に化けるとそれこそ見た目にはヴァンパイアとわからなくなりますからね。
特に上級のヴァンパイアとなると気配で探ろうとしてもわかりませんし、強力な呪文も操ると聞きます。」
ライアーが合いの手を出す。
「なるほど」
まぁ、マリーなら浄化魔法で一掃できるから心配するほどのことでもないのだが。
「それくらいですね。あ、それからヘイルイースとの国境に行く時にも注意してください。
ヘイルイースとはちょっともめていて、騒ぎが起こるのは避けたいので」
「わかりました」
マリーが納得すると、唐突に女王が、
「そうですわ。せっかくですからあなたには城に泊まっていただきましょう。
いまからでは空いている宿屋を見つけるのは面倒でしょうから、・・・・」
と、城に泊まらないかと簡単に言ってきた。
「い、いえそんなおかまいなく。それに城に泊めてもらったことは無いので・・・・」
「いいんですのよ。そんなこと。あなたなら大歓迎ですわ。
いろんなお話も聞けそうですし・・・」
「フレイヤ様はたまに人を誘って語り合うのがお好きでしてね。どうぞ遠慮なさらず」
ライアーまでもが誘ってくる。こうなると断りきれないのがマリーの性分だ。
「はぁ・・・・・、ならお言葉に甘えて・・・・」
しかし、その城でとんでもないことが起こるとはマリーはこの時知る由も無かった。
― To be continued ―