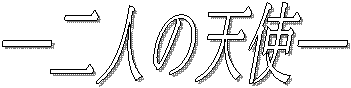
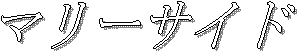
6・意外な真実
ドドドッ!キゥン!!
あわや対決というときに、意外なところから邪魔が入った。
「むっ!?」
「つっ、貴様は!」
私とヴァンパイア二人の間に魔力の槍を放ち、レイアとガルバディア、二人の剣を手のひらで受け止めたとんでもない人物。
「困りますよ。ガルバディアさん」
まるで道端でであった友人とでも話すようにその人物はいった。よくよく見れば、彼もまた貴族風の衣装をまとっている。目は線のように細く、口元には笑みを浮かべている。こいつも、ヴァンパイア。
「今、彼ら人間と戦ってはならぬと言われたはずですが?」
「邪魔をするな!シェザード!」
ガルバディアは激昂する。しかし、シェザードと呼ばれた男は動じずに、
「あなたがこのような失態を犯すと、後で追及されるのは私なんですよ?たまたま様子をみに出てきたら、こんなことをされている。困るんですよ」
「知ったことか。敵である人間どもを殺すことは我らの宿命だ」
「……。いいんですか?その台詞を“あの方”に報告しても」
一呼吸おいて言ったシェザードの一言にガルバディアの表情が変わった。
「……くっ!仕方あるまい」
今度はおとなしく剣を引いた。
「退くぞ!」
部下二人に言ってガルバディアは去っていった。
3人が消えた後、今度はレイアに対して彼は言った。
「申し訳ありませんねぇ、うちの問題人物が迷惑をかけたようで」
「貴様もな……」
レイアは剣を引き、返す刀で薙ぎ払う。しかし、シェザードはその一瞬で木々へと飛び上がる。すぐに見上げるがもう姿は無い。ついでに気配も完全に断っている。
『いやいや、そうですね。とにかくあなたもあなたですよ、ヴァレンタインさん。今ここでいざこざを起こしては後々まずいことになるのは判ると思いますが?』
「それはそちらの都合だろう?我々の知ったことではない」
シェザードの声だけがどこからか響き、それに答えるレイア。
『ははは、かもしれません。しかし判ってくださいよ。こちらとしても全面戦争は自殺行為なんですよ。どうしてもというのであれば私がお相手いたしますが?』
「結構だ」
レイアは言って剣をしまった。
『では、ご縁がありましたらまたいずれ……』
言って声が聞こえなくなった。
「誰なんですか?あれは」
気配が完全に消えてから30秒もして私は聞いた。
「シェザード。ヴァンパイアロード四天王……とでも言うんでしょうか?そんな感じの奴です。」
「……感じで済む方だったんですか?」
「まともなら済まないでしょうね」
この人って……一体。
ヴァンパイアは確かにいる。それを確認できただけ……でもないが、できたので私達は元の町へと戻ってきた。すでに日は傾き、夕餉の準備に町は混雑している。
「ご無事でしたか」
門番が声をかけてくる。
「ああ。変わりは無いか?」
「はっ。異常ありません」
「あらぁ、レイアさん。マリーさん」
ちょうどいい具合にフレイア陛下とライアーさんが出てきた。
「どうでしたか?収穫はありましたか?」
「ええ、もう少しで死ぬところでしたが……」
「ふふふ……、ご冗談を」
いや、マジで。
「そうだ。よろしかったらお食事を一緒にいかがですか?泊まるところもお決めになってないんでしょう?」
「え、えぇ」
そして、なんだかんだ言うわけで私は城へ宿泊することになってしまった。
豪勢な夕食の後、陛下は家臣に命じて書架からある本を持ってこさせて私に見せてくれた。
その本は分厚く、革張りがされている。しかも鍵まで付けるという厳重なものだ。
「これは?」
「クルドウェストとヘイルイース対ヴァンパイアとの戦いの記録の全てが収められた本です。
同じものがヘイルイースにもあります。」
陛下は言うと鍵を開け、本を開いた。
「そ、そんな物を私なんかに……」
「いーえ、話の種になればと思いまして」
ガク。
「レイアさんから話を聞いたと思いますが、はるか昔約3000年前にもなるでしょうか。国は今のように両国に分かれることもなく、混沌としていました。
王となろうとする者達によって多くの血が流れ、やがて“闇の眷属”、ヴァンパイアたちが介入してくるようになりました。彼らがいつどうして現れたのかは謎に包まれたままです。
しかし、ヴァンパイアたちは次第に勢力を拡大し、人間達もその脅威に気づき始めた頃にはすでに遅く、ヴァンパイアロードを核とした彼らは全領土の約半分を占領するまでになりました。」
彼女はそういうと、ページを繰り地図が書かれたところを開いた。世界地図なのだろう、しかし、中央部分からしみが広がるように黒く塗られていた。
「この黒いところ、その頃に作られた勢力図の様なものです。黒い場所はヴァンパイアが住み着き、近づけなくなりました。この頃のアルカスの森は別名「フォレストオブヘル」とも呼ばれていたのです。
人間とヴァンパイアの力の差は大きく、とても勝てないと思われていました。しかし、その頃の知恵者は突飛な事を思いつき、彼らが眠りにつく昼に、森を切り開いて行けばいいではないかと言い出しました。
むろんそんなことをすれば彼らは怒り狂うでしょう。ところがこれに賛同するものが一人二人と現れ始め、森は切り開かれていくこととなったのです。」
今度開いたページにはスケッチだろう、木を切る民衆が描かれていた。
「森の両端から森は少しずつ切り取られ始め、同時に人間達は自分達を守るための魔法の開発、武器の開発もはじめました。
その途中、様々な聖剣、魔剣が開発されたり禁呪とされる魔法までも開発されました。
そして、切り開きから数年がたち、いまのアルカスの森ほどの大きさまで切り開いたとき、ヴァンパイア達からの報復が始まりました。」
今度開かれたページには全体に戦争の絵が描かれていた。
「ヴァンパイア達は森を切り開かれたことによって著しく行動が制限され、徐々に数を減らしていきました。ただ、ヴァンパイアロードを倒さないことには何もならないことを知っていた人々は、ヴァンパイアの住む谷へと進軍を思案しましたが、そこははるか地下の洞窟。むろんヴァンパイア達も黙ってはいないでしょう。そういった理由で突撃は却下されたのですが、一人だけいたのです。無鉄砲なお人が。
名をラスベル。ヴァンパイアに親を殺されたという青年でした。彼は単身ヴァンパイアの洞窟に入り込み、ついには魔宮まで行き着きました。
しかし、彼だけではさすがに敵うはずもなく傷つき、追い詰められました。
その時、光が弾け一人の少年が魔宮に飛び込んできました。彼はヴァンパイアロードを簡単にねじ伏せると、封印をしてしまったそうです」
開かれたページには、封印されるヴァンパイアロードと一人の少年が描かれている。
「封印を施した彼はラスベルに言いました。
『私はコイツを封印できても滅ぼす技術を持っていない。もし、私と同じく“天使”に魅入られたものが来たならその者に頼め。そしてその時、わたしは戻ってくるだろう』と。
そして、彼はラスベルに二本の剣を授けたそうです。白と黒の剣。『右手に光る希望の光』、『左手に抱く無限の闇』それぞれそう呼ばれているそうです。
もし倒すのなら一度封印をとかないといけない。それが絶対条件だ。と言い残して彼は去りました。」
開かれたページには、二本の剣が描かれていた。白く光り輝く剣と、燃えるような闇を纏う剣。
「……右手に光る希望の光、……左手に抱く無限の闇。か」
私はなんとなしにつぶやいた。そのとたん頭の中に妙な反応があった。
「ん?……」
思わず顔を上げて周囲を見回す。
「お気づきになりました?」
「は?!」
「あるんですよ、この城に。“右手に光る希望の光”が」
「へ、陛下!!?」
さすがに今の一言は聞き捨てならなかったらしい。
「恐れ多くも、あの剣のことを部外者に話すのはちょっとどうかと思いますが……」
「ふふふ、いいじゃありませんか。」
その時メイドさんが入ってきて、部屋の準備が整ったと伝えてきた。
「それでは今日はこの辺にしましょうか。ごゆっくりお休みになってくださいね」
言われるまま案内されたのはいいのだが、やはり好奇心は押さえきれず、私は夜の城を徘徊する事にした。
―To be continued―
2002/03/08