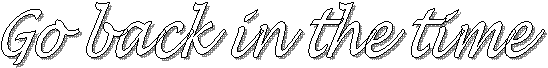
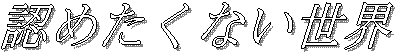
9・アリス=ハイランド
首都ガリウスト。全ての事の発端はこの町にある。エルフの長寿の秘密を知ろうとする愚かな行為。そのために殺されていった多くの犠牲。今終わらせなければ、エルフと人間は全面戦争でもしかねない。
そのために元宮廷魔道士でありながら、エルフ狩りを反対したハイランド導師のところへあたし達は向かっている。
首都の中では一切エルフのにおいをさせてはいけないので、今回ラミアはアジトに他のエルフたちと一緒に待っている。あたしのほかにいるのはラウル他、数人の同志達。向かう先は一箇所!ハイランド邸である。
町に入ってから気づいたことだが、やたらと傭兵だの、警備兵だのが多い。やはりエルフが一人でもいればすぐにとっ捕まえる算段でいるんだろう。
「待ちな。そこの」
いきなり目の前に大男が現れて道を塞いだ。
「お前ら、少しだがエルフの匂いがする……。」
「!?」
いきなり何を聞いてくるんだと思っていると、
「当たり前だ。ついさっきエルフを売り飛ばしてきたところだからな。匂いが染み付いたらしい」
「ちっ……。そうかい」
言ってどこへともなく去っていく。唖然とするあたしにラウルは、
「ここの連中はエルフに関してはかなり敏感な五感をしてるからな。注意しとけ」
妙に納得してしまう。
少し郊外にでたあたりにハイランド邸はあった。やはり元宮廷魔道士であるだけあり、豪勢な館だ。
「何者だ」
門を警備していた兵が誰何してくる。
「ラウルと申します。例の件でハイランド様にお目通り願いたい」
それを聞くと、門兵は中の館へと入っていった。確認に行ったのだろう。数分して門兵が戻ってきた。
「よろしい。通れ。」
そして、すれ違いざまに、
「エルフに自由を……」
聞こえるか聞こえないかの境の声で門兵はそう言った。なるほど、門兵まで信頼している人で固めたか。
「よくいらっしゃいました。私は執事のセバスチャンと申します。」
屋敷に入ってすぐに執事と名乗る人に会った。しかしセバスチャンとは、思いっきり執事してます!て感じだなおい。
「お嬢様は現在鍛錬場におられます。ご案内しましょう」
言われるままについていくあたしたち。
「ところでお尋ねしたいことがあるんですけど」
あたしは唐突に切り出した。
「はい。何でございましょう」
「どうしてハイランドさんはエルフの保護を唱えたんですか?」
「おい!何を失礼な!!」
ラウルが静止したが、セバスチャンは、
「そのことでございますか。……お嬢様はご幼少の頃、森で迷われたことがございましてね。
寂しくて泣いているところをエルフに発見されたのです。しばらくして、お母様であらせられるユリカ様の元へ無事に届けられたそうです。宮廷魔道士をなされていたユリカ様は債務を投げ出してまで、お嬢様の行方を捜されました。
その経験がお嬢様をエルフ狩りというものを反対させた理由でしょう。」
「なるほど。……って、じゃこの家は親子二代で宮廷魔道士をしてるの?」
「はい。ユリカ様は多大な功績を残され、この屋敷を建てられたのです。そしてお嬢様がお生まれになり、類まれな魔法の才能により、17歳にして宮廷魔道士に採用されたのでございます。」
「てことは、そのお嬢様ってまだ17歳!?」
「そうです。……つきました」
ついた先は、結構大きなドアで仕切られた部屋だった。コンコンとドアをノックするセバスチャン。
『誰?』
中から返ってきた声、聞いてビックリあたしにそっくりな声をしている。
「お客様をお連れしました」
『どうぞ』
ドアを開け、あたしを促すセバスチャン。言われるままに中へと入っていき、
ヒュッ!
「!!?」
いきなり目の前に何かが突き出された。よくよく見れば槍の穂先である。あ、……アブな!!
槍を突き出したのは背格好はあたしにそっくりだが、黒髪はストレートで髪留めもしていない女性だ。
「いらっしゃい。」
槍を突き出した格好のまま笑顔で言い放つ彼女。
「……ど、どうも」
どことなく怪しい彼女だが、槍の腕は本物らしい。
「お嬢様!!何をなさるのですか!お客様に対して」
彼女は槍を引き、石突でカツーンと床を叩くと、
「ちょっとしたコミュニケーションじゃない。そんなに慌てなくてもいいわよ」
「ですからそれがいけないのです。宮廷魔道士であったころも、そのような言動で目を付けられていたでありませんか!」
「うるさいわねぇ……、過ぎたことをグダグダと……」
目の前で繰り広げられる問答無用の“口撃”に唖然とするあたしたち。……あ、頭痛してきたし。
『あのう……』
ほとんど同時にあたし達は声をかけた。ハッとこっちを振り返る二人。
「こ、これは失礼を。こちらにおられる方が、アリス=ハイランド様でございます」
「アリスよ。よろしくね」
槍を持ち直して彼女、アリスは言った。
「で?何しに来たの?」
「ですからお嬢様!」
「セバスチャンはお茶の用意でもしてきてくれない?」
「……かしこまりました」
半分あきらめた風に言うと、部屋から出て行くセバスチャン。
「さて、邪魔者が消えたところで本題に入りましょうか?」
彼女は槍を、壁に設置された鎧の手に差し込む。
「どう?方々での活動は」
いきなり真面目モードに入ったかと思うと、ラウルと数人から方々の状況を聞き、逐一メモを欠かさず取っていた。
「……というしだいで、昨夜宿を壊滅させました」
「エライ!ご苦労様。」
「き、恐縮です」
「で?こっちの人は?」
と、羽ペンであたしを指した。まるで今気づいたかのように興味の視線を浴びせてくる。
――思ったより、キレるひとかもしれない。
「サリナよ。よろしく」
と、あたしは手を出した。
「よろしく、サリナさん。協力には感謝するわ。」
言って握手をする。と、手を合わせたとたんに妙な感覚が頭の中を走った。――心を読まれたか!?
しかし、そうではないらしい。彼女も不思議な顔をしている。
これは分からないままにしたほうがよさそうだ。
「……とにかく、サリナさんみたいに強い人が入ってくれると戦力が大幅にUPするわ。そろそろ決行できるかも」
「決行、て何するの?」
「決まってるじゃない。この国を終わらせるのよ!」
いすから立ち上がって叫ぶ。
「人間とエルフ。共に生きている者どうしが手を取り合って生きていける世の中を作る!そのためにこの国を終わらせるのよ!!」
『おぉ!!』
いつかどっかでサリナ自身が叫んだ言葉とそっくり同じことを叫ぶアリス。答えるラウル達。
「で、あなたの得意分野は?」
唖然とするあたしに指を突きつけて言うアリス。
「え、得意分野? 一応魔法全般と近接戦闘だけど」
「よろしい!」
はぁ?
あたしの内心の疑問を残したまま、アリスは心のたけをぶちまける。しかし、一貫して言えるのは彼女は心からエルフの保護を祈っているということだ。そして、
「……そのためなら、世界中を敵に回してもいいわ!」
とのこと。たしかにあたしの先祖かも……。
一段落して、セバスチャンの持ってきたお茶を飲みながら、あたしはその作戦の詳細を話してもらった。
「今ここまま城に攻め込んでもいいんだけど、それには邪魔な奴が一人いるのよ。」
と、一瞬悲しそうな顔を見せる。
「誰?」
あたしは聞いた。
「え、えぇ、そいつは現宮廷魔道士のイライザ=ハイランド。あたしの叔母よ」
「えぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ!!?」
恥も外聞もなくあたしは絶叫していた。おかげで全員がひっくり返り、お茶までも散乱する始末。ま、それだけ驚いたのだが。
「あ〜んたも強烈ね。かなり」
耳を押さえながらアリスが言った。
「だって、まさか叔母とやりあおうっていうんじゃ!?」
「そうよ。だから言ってるじゃない」
「待ってよ。なんで叔母と戦うの?」
「あの人も不老不死の薬になるって、エルフ狩りに賛成した一人なのよ。
親子二代が宮廷魔道士になるって本来ありえないことなんだけど、この国の王は私たちが使う“金色の翼”に興味を持っちゃってね。
元々母さんが開発した術なんだけど、ハイランド家の女性にしか扱えないって言うんで、我が家の秘術になったの。そこで出てきたのが叔母さんよ。三つ上の兄に嫁いできた彼女も結構な魔道士だったらしいわ。試しにって言うんで母さんが“金色の翼”を仕込んでみたところが発動しちゃったの。
私の場合ちっちゃい頃から叩き込まれてきたから今は普通に発動できるんだけど、彼女の場合は槍の力が必要なのよね」
「槍?もしかして魔力を持った槍?」
「そう。この国で宮廷魔道士が代々受け継いできた槍、“英雄の槍”っていうんだけど、とんでもない魔力を持った槍なの。常人が使ったら国一つふっ飛ばしかねない代物なのよ。」
「そんな物をあなたが使ってたの?」
「冗談!ちょっとした儀式とかそういうことにしか使ったことは無いわ。
でも、叔母さんは違う。ちゃっかり自分を売り込んだ叔母さんは槍の力で強くなってしまった。」
「で、邪魔だと」
「そうよ。母さんは叔母さんを説得しに行って、逆に反逆罪で牢へ直行するはめになるし。あのアバズレはぁぁぁ」
と、手を握り締めてくやしがる。……ていうか年頃の女が言う台詞か?
「とにかく、彼女を何とかして倒さない限り王はおろか大臣達にさえ近づけないのよ」
「なるほどね。ところで、その兄っていうのは?」
「……死んだわ」
思いっきりその場の空気が沈んだ。
「あ、ごめんなさい」
謝るあたしに笑顔を見せて彼女は、
「いいのよ。医者の話じゃ、“キュウセイシンフゼン”とかいう難しい病気らしいし」
お茶に伸ばした手が止まる。
「急性心不全!?」
「知ってるの?」
「だってそれって……、いえ、なんでもない」
急性心不全といえば、心臓に何らかの機能障害が起こって血液の供給が十分に行われないことを指す。
その“何らか”とはなんなのか。殺しだって急性心不全の一端である。
アリスは他の人たちと話を始めている。そんなアリスを横目で見ながら、あたしは自分の先祖が背負った運命というものを感じていた。
―To be continued―
2002/02/12